
今回は、柔軟な発想で「さまざまなアイデアが浮かんでくる」「色々な視点から見ることができる」など、正解は”ひとつではない”物事の考え方をお伝えできればと思います。
「もっと柔軟に考えられたらな…」
「行き詰まったとき、突破口を見つける方法が知りたい」
そんなときに役立つのが ラテラルシンキング(水平思考) です。
今回はその意味や具体的な使い方を、分かりやすく解説します。
ラテラルシンキングとは?
ラテラルシンキング(Lateral Thinking)は、直訳すると「水平思考」。
イギリスの思考研究者 エドワード・デ・ボノ が提唱した発想法です。

ロジカルシンキングは「垂直思考」ラテラルシンキングは「水平思考」と呼ばれているらしい。ふむ。
答えが1つではないのがラテラルシンキング
●一般的な「ロジカルシンキング(論理的思考)」は 筋道を立てて縦に掘り下げる思考
ロジカルシンキングは主にデータや経験から情報を整理して改善提案、実行へ移すための手段として使われる考え方です。
「何が原因かわからない」「どう改善したらいいかわからない」など、わからない事を明確にしてくれる手法でもあります。
そこから導き出してイノベーションしていくのも大切です。
ロジカルシンキングについてはこちらも読んでいただければと思います。
●「ラテラルシンキング」は 視点を横に広げ、常識にとらわれないアイデアを生み出す思考 のことを指します。

トンチの利く一休さんはラテラルシンキングで無理難題とされていた課題をクリアしていったのだね✨
よく言われる例として、「オレンジを13個3人で平等に分けるとしたらどうしたらいいか?」🤔
色々な考え方があって正解が複数あるラテラルシンキングの1つに
〇ジュースにして等分にする
という答えにたどり付いたお方が。
この発想を思いついたのは小学生にもなっていない子供だったそうです。
このように、常識やいままでの固定観念、固定概念を取っ払って枠を外しててあげた方が素晴らしいアイデアが思いつく可能性があります。
特に日本の教育は正解を導くために勉強をする事がほとんどですので日常の物事を多角的に見ると意識をしてみてください。
例で理解するラテラルシンキング
たとえば、「レストランの売上が伸び悩んでいた」とします。
●ロジカルシンキング的発想
- 広告を強化しよう
- メニューの価格を下げよう
もちろんこの考え方で改善できる事はありますが、限界が出てきます。
特にメニュー価格を下げようとすると他のコストをどうするかまた別の問題も出てきてしまう。
でも、「宣伝力が足りない」「メニューの価格を他店と比較しコストを抑える必要がある」といった”データを元に考える”ことができた結果。
ロジカルシンキングの場合”根本的な原因を考える”ことができますので、これも「使い方のバランス」が大事です。
●ラテラルシンキング的発想
- 昼はラーメン屋や定食屋、夜はバーとして二毛作営業する
- 客が自分で調理する体験型レストランにする(焼き肉店などが典型的)
- 料理ではなく“空間”を売る(カフェなどコミュニティでの会話による楽しい時間や仕事がはかどる空間)
このように、従来の枠を超えた斬新な答えを導けるのが特徴です。
もちろん根本的な見直しは必要ですが、新しい発想から新しい挑戦をした結果成功されている方々もたくさんいます。
新しいアイデアが思いつく事で視野が広まるので日頃から考える力を鍛えていただければと思います。
ラテラルシンキングが役立つ場面
- 新規事業や商品企画のアイデア出し
- 問題解決が行き詰まったときの突破口
- 人間関係や働き方を変えたいとき
- アート・デザイン・クリエイティブな活動
ラテラルシンキングの4つの基本技法
日常で考えてもみなかった物事を習慣づけることもできます。
何気ない場所からでも「なんで〇〇がこうなったのだろう?」「逆にこうしてみたらどうかな?」など考える事を意識してみてください。
1.前提を疑う
「そもそも本当にそうなのか?」と常識をひっくり返す。
「なぜ星が動いているのか?」
「そもそも宇宙がまわっているのか?」
を考え直した結果、本当は地球が自転公転しているのを発見できました。
これはとんでもない規模のお話ですが🫣考えるきっかけって本当に大事です。
- 子どもや初心者の視点で「なぜ?」を繰り返す
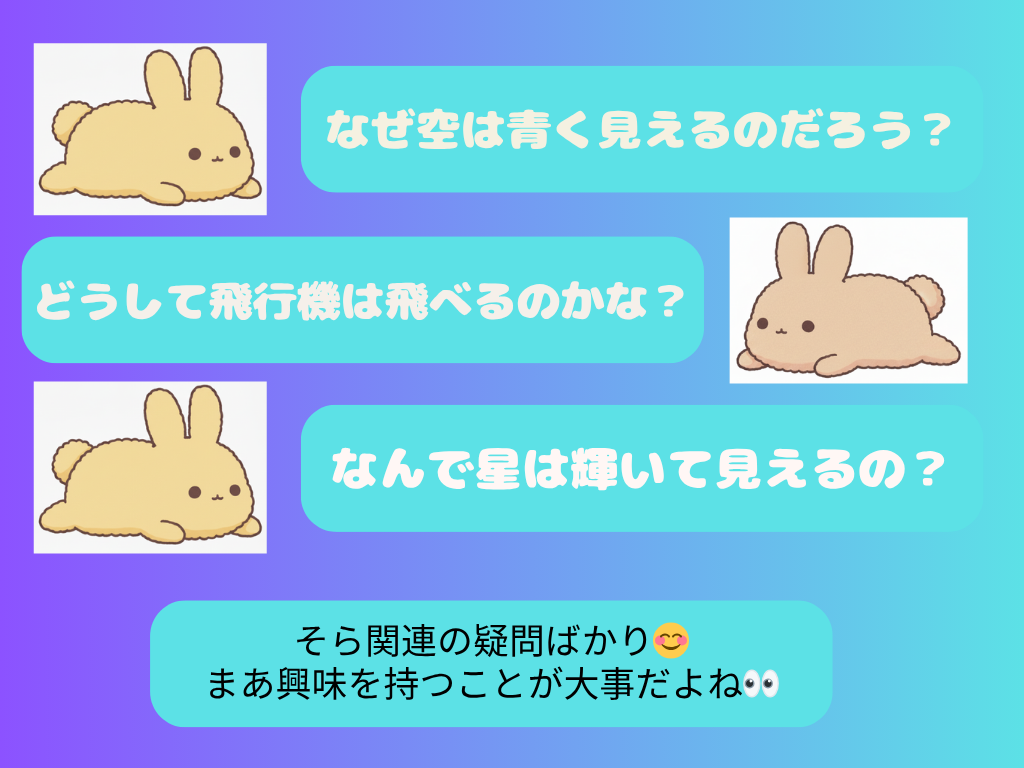
2.逆転させる
「普通ならこうする」をあえて逆にしてみる。
- 不便を売りにする
- 普通は「便利にする」ことを考えるけれど、あえて「不便だからこそ価値がある」とする。
- 例:スマホ断ちできる“圏外カフェ”、わざとネットが遅い「デジタルデトックスホテル」。
- 売らないことで売る
- 商品を直接売らず、無料提供して別の収益モデルを作る。
- 例:フリーミアムアプリ、無料のフリーペーパーが広告収入で成り立つ。
- 足りないからこそ強みになる
- 資源や人手が不足していることを逆手にとる。
- 例:人手不足を逆に“完全予約制・限定対応”として高級感を演出。
- 結果から逆算する
- 通常は「どうすれば目標に到達できるか」を考えるが、逆に「失敗する方法」を考えて、それを避ける。
- 例:成功するための“やってはいけないリスト”を作る。
- あえて逆の客層を狙う
- 子ども向け→大人向けにする、都会向け→田舎向けにする。
- 例:子ども用だったキャラクターを大人向けグッズに展開。
また、逆転の発想から生み出され大ヒットした商品もあります。
⌚ G-SHOCK(カシオ)
●従来の常識
- 腕時計は精密機械で壊れやすい → 大切に扱うもの。
- 落とすと壊れる、衝撃に弱いというのが「当たり前」でした。
●逆転の発想
- 「壊れない時計を作ろう」
- 普通なら「精密=壊れやすい」を前提にするのを、逆に「強さ」を主軸に発想。
- 中空構造・衝撃吸収素材・モジュールを浮かせる構造などを採用。
●結果
- 「落としても壊れない」という逆発想が世界的なヒットに。
- ファッション性もプラスされ、ミリタリー・アウトドアからストリートカルチャーまで広がりました。
🛏 エアウィーブ
●従来の常識
- マットレスはウレタンやスプリングが主流。
- 「柔らかい寝心地=高級」「ふかふかが良い」というイメージが強かった。
●逆転の発想
- 「硬めで反発力があるほうが快眠できる」
- 素材にプラスチック繊維を採用 → 体をしっかり支え、寝返りが打ちやすい。
- 「ふわふわ=良い睡眠」という前提を覆し、「寝返りが自然にできる硬さ=快眠」に転換。
●結果
- トップアスリート(例:フィギュアスケートの浅田真央選手)が愛用し話題に。
- 医療・介護の分野にも展開し、支持を拡大。
✨ 共通する逆転ポイント
- 「常識」を疑った
- Gショック:壊れやすい時計 → 壊れない時計
- エアウィーブ:柔らかい寝具が良い → 硬めで寝返りしやすい寝具
- 欠点を強みに変えた
- 時計の「衝撃」=壊れる → デザインと性能の象徴に
- マットレスの「硬さ」=寝心地が悪い → 快眠の条件に
- 新しい市場を作った
- Gショック:タフネスウォッチ市場
- エアウィーブ:高反発マットレス市場
●日常の「当たり前」を紙に書き出して、1つ逆転させてみる
ただ日々過ごすだけでなく、日頃の生活でも逆転の発想を考えてみてくださいませ。
3.組み合わせる
違う分野のアイデアや仕組みを掛け合わせる。
なかなかペンとりんごとパイナップルを組み合わせて歌をつくるという発想は思いつきませんが、こういった斬新な組み合わせも大事にしていただきたいです。
🏠 家事・日常 × 意外な組み合わせ
掃除 × 香り
掃除用品にお好みのアロマを染み込ませる → 掃除中に香りも楽しめる。
洗濯 × デザイン
ハンガーや洗濯物干しをオシャレにする → 部屋のインテリアとしても楽しめる。
料理 × 収納
調理器具と食材をセット化してスタンドに置く → 「この棚を開ければ料理完成」の感覚。
片付け × アート
物を収納する箱や棚を色分けや模様付きにして、片付けながら部屋がアートになる。
ゴミ捨て × コミュニケーション
ゴミ袋にメッセージやイラストを描く → 家族や同居人との遊び心コミュニケーションに。
アイロン × 香り
アイロン時に香りシートを同時に挟む → 衣類が整う+良い香りでリラックス。
掃除 × 運動器具
モップや掃除機に軽い抵抗をつける → 掃除しながら軽い筋トレになる。
洗濯 × 植物
室内干しの周りに観葉植物を置く → 湿度調整と空気清浄、見た目も癒される。
キッチン × 音
フライ返しや鍋敷きに音が鳴る工夫 → 料理するだけで音楽のようなリズムを楽しむ。
片付け × 道具
収納箱に重さセンサーを付けて、重さでどれだけ物が減ったか分かる → 達成感を演出。
家事として例をあげましたが、つまらないと感じているものも組み合わせの工夫次第で楽しい時間に変えることもできるのがラテラルシンキングです。
「これじゃ満足できないね!」という方も自分のアイデアで楽しい時間をつくり、アウトプットしてみてはいかがでしょうか。
家事がつまらないという方々のためにもなるかもしれません。
●ランダムに選んだ単語をテーマと結びつけてみる
4.偶然を利用する
●思いついたことやランダムな要素から発想を広げる。
偶然を何かに関連づける力。
大陸がもともと一つだったとわかったのは、偶然地図を見ていたら大陸同士の端がパズルのようにつながるということを発見したからです。
このように、「ん?」とちょっとした物事でも考えてみると「偶然か…」「必然か…」哲学みたいですが発見する力が発揮できるかもしれません。
●「もし◯◯だったら?」と仮定を設定して考える

ゲーム感覚で行うと、柔軟な発想力が育っていきます。
まとめ
ラテラルシンキングとは、
「正しい答え」を探すのではなく、
「新しい答え」を生み出すための思考法です。
ロジカルシンキングと合わせて使うことで、
「現実的かつ独創的な解決策」を導きやすくなります。
ラテラルシンキングとは?
- 答えが1つではないのがラテラルシンキング
- 例で理解するラテラルシンキング
- ラテラルシンキングが役立つ場面
ラテラルシンキングの4つの基本技法
- 1.前提を疑う
- 2.逆転させる
- 3.組み合わせる
- 4.偶然を利用する
今日から少しずつ、思考の幅を広げていただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!!



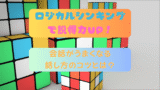
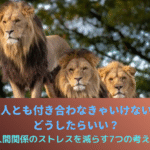

コメント